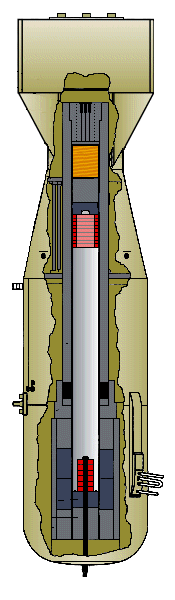核融合炉
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。
出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年3月) |
核融合炉(かくゆうごうろ)は、現在開発中の
原子炉の一種で、
原子核融合反応を利用したもの。21世紀後半における実用化が期待される未来技術の1つである。
重い原子たる
ウランや
プルトニウムの
原子核分裂反応を利用する
核分裂炉に対して、軽い原子である
水素や
ヘリウムによる
核融合反応を利用してエネルギーを発生させる装置が核融合炉である。現在、日本を含む各国が協力して国際熱核融合実験炉
ITERの
フランスでの建設に向けて関連技術の開発が進められている。ITERのように、核融合技術研究の主流の
トカマク型の反応炉が高温を利用したものであるので、特に熱核融合炉とも呼ばれることがある。
太陽をはじめとする
恒星が輝きを放っているのは、すべて核融合反応により発生する熱エネルギーによるものである。これは核融合炉が「地上の太陽」と呼ばれる由縁である。恒星の場合は自身の巨大な重力によって反応が維持されるが、地球上で核融合反応を発生させるためには、人工的に極めて高温か、あるいは極めて高圧の環境を作り出す必要がある。
核融合反応の過程で
高速中性子をはじめ、さまざまな高エネルギー粒子の放射が発生するため、その影響を最小限に留める必要がある。そういった安全に反応を継続する技術、
プラズマの安定的なコントロールの技術、
超伝導電磁石の技術、遠隔操作保守技術、
リチウムや
重水素、
三重水素を扱う技術、プラズマ加熱技術、これらを支えるコンピュータ・シミュレーション技術などが必要とされ開発が進められている。
核融合反応
原子番号28ぐらいまでの軽い
元素では、
核子一個あたりの結合エネルギーが比較的小さいので、原子核融合によって余分なエネルギーが放出される可能性がある。しかし、原子核の電荷が互いに反発して反応を阻害するため、実際にエネルギーを取り出して利用できるような形で反応を起こすことが可能なのは、電荷がごく小さい
水素や
リチウムなどに限られると見られている。実際に核融合反応で発電するためには、原子核が毎秒1000km以上の速度でぶつかりあう必要がある。プラズマの温度を高くするために外部から加えたエネルギーと核融合反応により発生したエネルギーが等しくなる条件を「臨界プラズマ条件」と呼び、D-T反応(
重水素と
三重水素の反応)では「発電炉内でプラズマ温度1億℃以上、密度100兆個/cm
3とし、さらに1秒間以上閉じ込めることが条件」と、いうことになる。2007年10月現在、この条件自体は
JT-60及びJETで到達したとされているが、発電炉として使用出来るまでの持続時間等には壁は高く、炉として実用可能な自己点火条件と言われる条件を目指し挑戦がつづいている。
利点
- 核分裂による原子力発電と同様、二酸化炭素の放出がない。
- 核分裂反応のような連鎖反応がなく、暴走が原理的に生じない。
- 水素など、普遍的に存在する資源を利用できる。
- 原子力発電で問題となる高レベル放射性廃棄物が継続的にはあまり生じない(もっとも古くなって交換されるダイバータやブランケットといったプラズマ対向機器は高い放射能を持つことになる。ただし開発が進められている低放射化材料を炉壁に利用することにより、放射性廃棄物の浅地処分やリサイクリングが可能となる)。
- 従来型原子炉での運転休止中の残留熱除去系のエネルギー損失や、その機能喪失時の炉心溶融リスクがない。
などが挙げられる。
欠点
- 超高温で超高真空という物理的な条件により、実験段階から実用段階に至るすべてが巨大施設を必要とするため、莫大な予算がかかる。
- 反応条件が緩やかなD-T反応でも1億度程度の高温でなければ十分な反応が起こらず(反応条件が厳しいD-D反応では10億度、太陽内部の陽子-陽子連鎖反応を人工的に再現するには50億度以上)、そのような高温状態では物質はプラズマ状態となる
- 炉壁などの放射化への問題解決が求められる(後述)。
安全性・危険性
- 反応の停止
- 核融合反応は核分裂反応と違って反応を維持するのが技術的に大変困難であり、あらゆる装置の不具合や少しの調整ミスが自動的に核融合反応の停止に結びつき、簡単には反応を再開出来ない。これはむしろ安全にとっては良い特性であり、現在の核分裂を使った商業用原子炉の根本的な危険性とは無縁である。
- 放射性廃棄物
- 核融合反応で発生する中性子は、核融合炉壁及び建造物を放射化する。放射化された核融合炉周辺の機械装置や建物が安全に本来の機能を発揮出来るような設計が求められる。たとえばITERにおいては2万トンの低レベル放射性廃棄物を発生させると推測されている(東海発電所の廃止措置に伴う物と同程度の量)。今後建設されるそれらの建物はすぐに廃棄できず既存の原子炉と同様30年程度の冷却期間が必要だと予想される。地層処分などの問題は現在の原子炉と同じ様に、費用の問題や環境汚染対策が必要である。
- 古くなったダイバータやブランケットは定期的に放射性廃棄物として発生するのでこれらの処理も必要となる。これらの発生頻度を最小化する部材技術の開発が求められる。また、三重水素の燃料化プロセスでも放射性廃棄物への配慮が必要となる。
- 三重水素の放射性
- 三重水素は放射性物質であり正しく管理される必要がある。特に環境への漏洩阻止は重要である。三重水素は容易に通常の水素と置き換わるので、漏洩した場合には三重水素を含む水や有機物が自然界で生じ、これらは生物の体内に容易に取り込まれる。三重水素水が生物に取り込まれた場合、通常の水と化学的な相違点は僅かであるため特定の臓器などに蓄積されたり体内で濃縮されたりする事はほとんどなく、通常の水と同じように排出される。生物が三重水素水を取り込んだ場合に半分が排出されるまでの時間(生物学的半減期)は、人の場合10日から14日程度とされる。また、三重水素を含む有機物を取り込んだ場合には、その有機物に見合った蓄積性と濃縮性を示す。ただし、三重水素は拡散しやすいため一点に留まらず、また水素が地球上に遍在するために三重水素が環境に放出されても希釈が早く生物濃縮なども受けにくい。このため、特定の食品などに濃縮されることなどは考えにくい。
- 三重水素の核兵器への転用
- 三重水素は初期の核融合爆弾にも用いられたが、後に、入手性/取り扱いともにより容易な重水素化リチウムが利用されるようになったため、わざわざ三重水素が水爆に利用されることは考えにくい。また、現在の技術では核融合爆弾の起爆には原子爆弾を用いる外に手段が無いため、既存の核保有国以外が製造することは容易ではない。ただし、通常の放射性物質同様、三重水素を原料にした汚い爆弾は容易に作ることができるがエネルギーが低いため皮膚すら貫通できず、他の材料を使った汚い爆弾に比べると実害は少ないとされる。
- 運転中の放射線
- 核融合炉の運転中はプラズマから強烈な中性子線が放射されるため、さまざまな防護措置をとってもある程度漏れることが予想されている。現状、ITERで予定される運転中の放射線は、敷地境界で1年間に約0.1ミリシーベルト以下と自然放射線の10分の1に当たる量である。
- 超伝導電磁石
- 超伝導電磁石とそれを支える構造支持体は運転中に連続して大きな力を受け続け、起動や停止時にはその変化に応じた力学的ストレスを受ける。また異常に応じて磁力を突然切る場合は、瞬間的に大きな変化に耐えねばならず、中性子を浴び続ける構造支持体が脆化しても支えきれるだけの安全度を確保することが求められる。
核反応
核融合炉において,使用が検討されている反応は主に以下の3つである。なお、以下 Dは重水素、Tは
三重水素(トリチウム)、pは水素原子核、nは中性子、Heは
ヘリウムである。
D-D反応
- D + D
 T + p
T + p
- D + D
 3He + n
3He + n
自然界でも原始星で起きている反応の一つである。核融合炉として使用する場合、資源の入手性が非常に良いが、反応条件が厳しく、D-T反応の10倍厳しい反応条件を達成する必要がある。D-D反応で生ずる
トリチウム、
ヘリウム3 をその場で燃焼させる
触媒式D-D反応が検討されている。なお、JT-60を含む多くの核融合開発を目的とした実験装置において、重水素を使う実験が行われている結果、この反応が起きている。もちろん、投入エネルギーを回収出来る程ではない。
D-T反応
- D + T
 4He + n (14MeV)
4He + n (14MeV)
反応条件が緩やかで、最も早く実用化が見込まれている反応である。核融合炉として使用する場合トリチウムの入手性に課題がある。トリチウムは、自然界においては、大気の上層でわずかに生成されるのみであり、半減期の短い放射性物質であるため事実上採取は不可能である。また、
高速中性子が生成するため、炉の材質も検討が必要となる。現在検討されているトリチウム入手法は、核融合炉の周囲を
リチウムブランケットで囲み炉から放出される高速中性子を減速させつつ核反応を起こし、
- 6Li + n
 T + 4He + 4.8MeV
T + 4He + 4.8MeV
- 7Li + n
 T + 4He + n - 2.5MeV
T + 4He + n - 2.5MeV
トリチウムを得ることである。このときブランケットは高速中性子を減速して遮蔽し、燃料を生産し、反応熱を取り出すと言う3つの役割をすることになる。
欧州トーラス共同研究施設および
TFTRにおいてはこの反応を主反応とするような実験が行われた。
D- He反応
He反応
- D + 3He
 4He + p
4He + p
イオン温度が10億度の条件において、反応断面積がD-D反応の5 -
6倍程度の条件とD-T反応程ではないが比較的起こりやすく、発生するエネルギーも荷電粒子である陽子が担い放射性物質も出ないので炉が扱いやすいこと(但し副反応のD-D反応で中性子が発生する)と、直接電力にエネルギーを変換することが可能なことで注目されている反応である。しかしながら、地球上にはヘリウム3がほとんど存在しないことが大きな問題である。
アポロ計画の探査の結果
太陽風により
月には大量の
ヘリウム3が存在することが明らかになったが、実用化は非常に遠いと見られる。
中華人民共和国の
月探査計画はヘリウム3採取を最終目的にしている。
核融合反応の候補
下記の核融合反応が核融合炉で利用可能と考えられている。
- D + T
 4He (3.52) + n (14.06)
4He (3.52) + n (14.06)
- D + 3He
 4He (3.67) + p (14.67)
4He (3.67) + p (14.67)
- D + D
 3He (0.82) + n (2.45)
3He (0.82) + n (2.45)
- D + D
 T (1.01) + p (3.03)
T (1.01) + p (3.03)
- p + 6Li
 4He (1.7) + 3He (2.3)
4He (1.7) + 3He (2.3)
- p + 6Li
 4He + D + p - 1.5MeV
4He + D + p - 1.5MeV
- n + 6Li
 4He + D + n - 1.5MeV
4He + D + n - 1.5MeV
- D + 6Li
 7Li (0.6) + D + p (4.4)
7Li (0.6) + D + p (4.4)
- D + 6Li
 4He + T + p + 2.3MeV
4He + T + p + 2.3MeV
- D + 6Li
 2 2He (1.12)
2 2He (1.12)
- D + 6Li
 7Be (0.43) + n (2.97)
7Be (0.43) + n (2.97)
- D + 6Li
 4He + 3He + n + 1.8MeV
4He + 3He + n + 1.8MeV
- D + 6Li
 4He + 2D + n - 1.5MeV
4He + 2D + n - 1.5MeV
- 3He + 6Li
 24He + p + 16.9MeV
24He + p + 16.9MeV
- p + T
 3He + n - 0.8MeV
3He + n - 0.8MeV
- p + 11B
 34He + 8.68MeV
34He + 8.68MeV
(カッコ内は反応生成物のエネルギー MeV)
[1]
現状と問題点
現在最も研究が進んでいるのは、磁気閉じ込め方式の一種である
トカマク型であり、現在計画中のITER(国際熱核融合実験炉)もこの方式を用いている。
核融合の際に発生する中性子が炉壁などを傷つけるためにその構成材質の耐久力が問題となるとの指摘がある。[誰?]とりわけITERでは前述の「D-D反応」よりも
反応断面積が約100倍大きい「D-T反応」を用いる計画であるが、D-T反応では
高速中性子が発生する。
この高速中性子により炉の構成材内部では使用温度等にも依存するが、「照射脆化」が進行する場合がある。つまり原子が弾き飛ばされ材料内部に「原子空孔」(vacancy)や「格子間原子」が生じ(「フレンケル対」)、弾き出しが連鎖衝突した結果発生するつながった「
格子欠陥」(「カスケード損傷」)により、これらの点欠陥集合体や析出物の形成等が生じることによって材料の降伏強度が高まるに伴い脆くなる。また構成材の原子が核変換を起こし発生したヘリウムガスが原子空孔と結びつくことによって材料の内部に空洞を形成し膨張する問題(
スウェリング)も発生する場合がある。こういった劣化が一定以上進めば、もはや十分な耐久性を維持出来ないために交換を必要とする。
また、脆化以外にも材料が放射化することから、低レベル放射性廃棄物が生成する問題も挙げられているが、低放射化フェライト鋼を用いることでITERのテストブランケットの構造材料は目処がたっている。[要出典][2]また、構成材内部とは別に炉壁表面でも問題が生じる。プラズマイオンが炉壁に衝突すると「物理スパッタリング」と呼ばれる炉壁材料原子のはじき出しが起こる。炉壁面に炭素素材を使用すると、水素同位体の入射でメタンやエチレンなどの炭化水素が発生して、炉壁が損耗する化学スパッタリングという現象も起こる。
その他、各種の閉じ込め方式があり、それぞれ各国で研究が進められている。日本では、核融合研究の中心は
日本原子力研究所の「
JT-60」(
トカマク型)、
核融合科学研究所などで進めている
LHD(
ヘリカル型)と、
大阪大学で研究が進んでいる
レーザー核融合である。
圧力の低いプラズマを保持することは比較的容易であるが、エネルギーとして利用可能な程度の圧力のプラズマを保持するのは難しく、前述のJT-60で、高圧力プラズマの保持時間は30秒程度である(この30秒という時間は加熱装置である中性粒子ビーム入射装置の稼働時間の上限で決まっている。現在ITERのために1000秒以上稼働できる装置を開発中である。)。また、保持のために投入するエネルギーに比較して反応により得られるエネルギーはまだ小さく(
エネルギー増倍率(Q値) - 1.25)、世界の各種装置で核融合利得1を若干超える程度である。
これらの課題については、ITERで研究が進められる予定である(ITERの目標値はQ値 - 10)。[要出典] [3]
1989年、
常温核融合の発見が世間をにぎわせたが、その後の
追試験で測定方法に欠陥があるとの認識が高まり現在は似非科学の一つとされ、ネイチャーをはじめとした主要な科学雑誌も常温核融合に関しては掲載拒否の方針を示している。
実用化に向けて
小型核融合炉について
ロッキード・マーチン社は2014年10月16日、10年以内にトラックに積み込める大きさの100メガワット級商用小型核融合炉を開発すると発表した
[4]。2013年2月7日に発表された
高ベータ核融合炉の続報である。
2015年
九州大学と
核融合科学研究所は、それまで理論的には予想されていながら実験で確認されていなかったプラズマの流れが磁場の乱れによって脆弱化する現象の観測に成功した
[5]。
2016年3月18日
文部科学省は現在の実証炉ITER(イーター)以降の次世代炉を
三菱重工・
東芝と共同で研究し2035年頃の建設を目指予定と
日本経済新聞が報じた
[6]
核融合炉の種類
- 磁場閉じ込め方式
- 慣性閉じ込め方式
- 磁気絶縁方式慣性核融合(Magnetically Isolated Inertial Confinement Fusion=MICF):慣性閉じ込め方式と磁場閉じ込め方式との混合型。迷走ホットエレクトロン(プラズマを構成する電子のうち、プラズマ中の他の粒子に衝突してエネルギーを失うよりもはやくエネルギーをもって流出する電子)は磁場を作り出すが、この磁場は熱伝導に対する絶縁効果をそなえている。そこでMICFは非常に高効率のレーザーを用いて2つのアイデア、つまり熱絶縁と慣性閉じ込めを同時に実現しようというもの。
AT&Tベル研究所研究員だった長谷川晃(2010年現在は大阪大学名誉教授)が理論を提唱した。
- レーザー核融合
- 荷電粒子ビーム核融合
- 球状収束型ビーム核融合
- フューザー
- Zピンチ核融合:米国サンディア国立研究所が保有するZマシンは、この方法で2003年3月に重水素燃料のみを用いた実験において核融合を達成した[7]。
脚注
参考資料